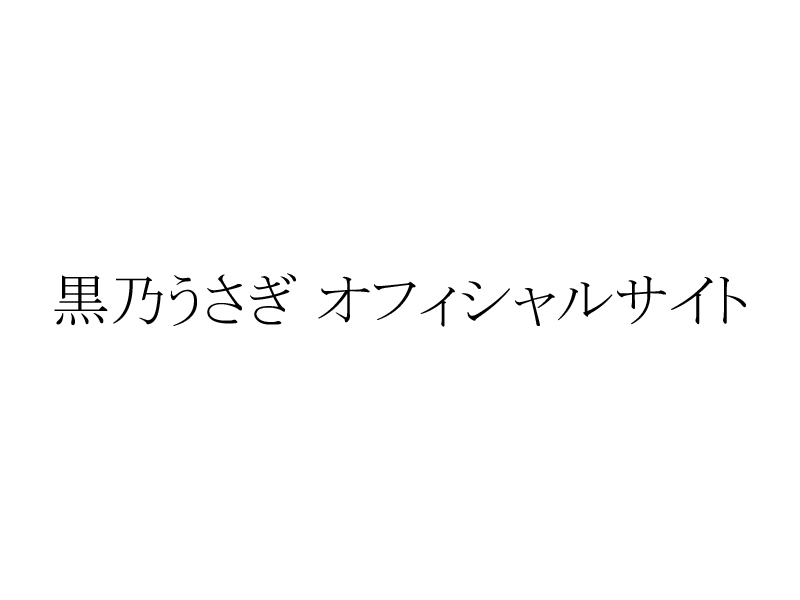~後編~ ぱらいそ
【6月17日 午後7時41分】
夕食を終えて、愛恵はルーティンとなっている音楽鑑賞を楽しんでいた。今日配信されたばかりのスーサイド・バニーズ、通称スイバニのアルバムをヘッドフォンで聴いている。
「フン、フフン♪ クライナーと風邪薬ー♪ 旧コマ劇場前広場に降り立ったー♪」
「愛恵ちゃんは今夜もノリノリねえ。ご飯は食べ終えたかしら?」
食器類を片付けるため、女性の看護士が巡回ついでにやってきた。彼女は入室に気付いていないので、肩をちょいちょいと指で叩く。
「わっ、びっくりした。ノックしてよー恥ずかしいじゃない」
「ノックしましたよ。音楽を聴いていたの? スーザンバンビですっけ、変わった歌詞ねえ」
「スーサイド・バニーズですー! 全然売れていないバンドだけど、あたしの心には刺さるの」
「おばちゃんも後20年若ければ理解出来るのにねえ、オホホ。あら? 今夜もご飯残しちゃったの?」
簡易テーブルに置かれた夕食は殆ど手がつけられていなかった。愛恵は一日を通して殆ど食事を摂らない。代わりに間食としてチョコレートをよく食べている。
「お腹は空かないの。それに、病院食って美味しくない。ゲロみたいな味がする」
「栄養とか考えて作られているから、好みに合わなくても我慢してほしいのだけど。いつもこの調子なんだから心配。明日はきちんと食べてね」
ベテランの看護士は怒るわけでもなく、食器を引き上げると、さっさと部屋を出て行ってしまった。ミュージックプレーヤーの電源をオフにすると、再び静寂が訪れる。
「……心配なんかしていないくせに。クソババア」
【6月17日 午後10時22分】
消灯時間を過ぎた頃、今夜もスタンドライトの明かりの下で愛恵は本を読んでいる。うつ伏せ状態になって、脚をばたつかせて上機嫌のようだ。
彼女のバイブルとも言える本、死後の世界について。胸をときめかせて、未だ見ぬぱらいそに憧憬を抱く。
「ふんふん……こんな場所もあるんだ。あたしの待ち望んだ楽園まで、残り一週間かあ」
「楽園はいいとして、さっきのあの態度はなっていないわ」
愛恵の頭上から声が聞こえる。天井へと張り付いて、逆様になったアンジュが話しかけてきた。死神に重力という要素はないのだろう。
「なぁんだ、もしかしてずっと傍で見ていたのかな。あの態度って何のこと」
「ここで看病をしてくれる人達は皆、貴女を助けようと、病気を治そうと必死でいるのに。自分の言動が心無いと思わない?」
「そんなことないわ。寧ろ、心無いのはあいつらの方だよね。延命をさせる目的だって、高額な治療費が欲しいだけよ。金、金、金。うざったい」
「……これはただの興味本位での質問だから、答えなくてもいいわ。どうして、そこまで歪んでしまったの?」
「ふふ、鬱屈にもなるよ。ねえ、どうして、こんなあたしが生きているの?」
「人は平等に産まれ、愛を育み、子孫を残すために生きているってのが通説ね」
「アンジュちゃんは本心でそう思っている? 子孫を残すって、二年以上前から生理も止まって、恐らく子供は産めないと言われているあたしに、残酷なこと言うんだね」
「だから通説よ。さっきの答えは建前で、私自身は思っていない。産まれた時点で優劣あるのが現実でしょう」
「正解だよ。人間のこと分かっているね」
愛恵は小さな声で呟く。今までアンジュに見せた中でも、一段と悲壮を帯びた顔だった。
「病気のせいで、この部屋から殆ど出られない。通学も諦めたし、将来働くことも無理。子供以前に結婚だって不可能よ。生きていることがナンセンス。無駄な労力でしかない」
「確かに愛恵の病気は治らない。だから、間もなく自死を選択する。それでも、私は全ての命に『無駄』なんてないと思うわ」
「じゃあ、私の命の意味を、天使様が教えてくれるの?」
振り向いた愛恵は目に涙を浮かべていた。アンジュの胸に手を当てて、トン、と軽く叩く。
「私の生きる意味を、存在意義を教えてよ」
「それは……自分で見付けるべきよ。私からは教えない」
「嘘吐き。教えないんじゃなくて、教えられないんでしょう? ねえ、そうでしょ」
「…………」
アンジュは何も反論をしなかった。愛恵はそれが肯定の返事だと解釈する。
「今夜は、この部屋から出てってちょうだい。あたしの視界から消えて」
「消えてと言うのは、愛恵の『願い』なの?」
「違う。違うけど、消えて」
「分かったわ、貴女が落ち着くまで、数日は戻らない」
アンジュは窓を乗り越えて飛び立った。愛恵は枕に顔を埋めて、声を殺して泣いた。
【6月19日 午前6時14分】
その日は朝から雨が降っていた。携帯のアシスタント機能によると、この雨は一日中降り続くらしい。まるで、愛恵の精神世界を表しているようだった。
人気声優がラジオパーソナリティーを務める放送で、今日から東京も例年よりやや遅めの梅雨入りが発表されたと言っていた。彼女は自分の死ぬ日が雨だったらどうしようと考えた。
「鬱陶しい時期ね。雨の日は湿気で髪もうねるし、最悪」
化粧ポーチからブラシを取り出して、丁寧に髪を梳かす。幼い頃は日課のようにママに髪のケアをしてもらっていたことを愛恵は思い出す。
「仕事が忙しいのは知っているけど、今月に入って一度もパパとママに会っていない。もうすぐ大事な娘が、この世から居なくなるんだよ」
まだ15年しか生きていない彼女の呟きは、弱々しく雨の音に掻き消されて沈んだ。
【6月19日 午前7時58分】
ピュロロロロと独特な美声でカナリアが鳴いている。餌の催促だった。
「ごめんねシェリー、忘れていたわけじゃないのよ。さあ、ゲージから出ておいで」
手に乗せて、そのまま自分の膝の上にカナリアを移動させた。餌を与えていると、若い看護士が部屋に入ってきた。間もなく診察の時間だ。
「おはよう愛恵ちゃん。もう起きて……えっ、それ何やっているの?」
「おはよう。この病室に天使様がやってきて、シェリーを生き返らせてくれたの。こんな話、信じられる?」
「そう……だったの、まあ驚いたわ。信じるわよ。天使って本当に存在するのね……」
看護士は目を見開いて心底驚いているようだった。そのリアクションを見て、愛恵は非常に気分が良くなった。
「毎日嫌な検査に耐えて、今までずっといい子にしていたもの。だから、天使様が願いを叶えてくれたの」
「いつも頑張って偉いわよ。病気なんかに負けないようしないと。検査を始めるから、その小鳥さんをゲージに戻して採血と心電図をしましょう」
「はぁい、ごめんね。検査の後にシェリーはまたご飯を食べましょう」
看護士はいつもより余所々々しい態度だった。それが愛恵には大変面白おかしかった。この人が数日後にジサツを知った瞬間、どんな反応をするのかと今から楽しみだった。
朝の検査を終えると、そそくさと部屋を出て行ってしまった。先日亡くなったカナリアが生き返った奇跡を、これから同僚に吹聴して回るのかと思うと自然と顔が綻んだ。
カナリアの噂は一日で病棟に広まった。翌日から腫れ物に触るような扱いをされていたことに、彼女は全く気付いていなかった。
【6月22日 午後5時33分】
いよいよ、ぱらいそへと旅立つ日が近付いてきた。最期の願いをどうするのか、愛恵は既に決めていた。
「こんなお願いすると、きっとアンジュちゃんはドキドキするだろうな。うふふっ」
「もうすぐ自死を迎えると言うのに、今日も幸せそうな顔をしているわね」
数日前に出て行ったアンジュが窓から戻ってきたところだった。すっかり機嫌を取り戻していた愛恵は、ニコニコ顔で話しかける。
「あっお帰りなさい、アンジュちゃん。そうよ、あたしは今とても幸せ」
「長年、死神業をやってきたけど、愛恵ほど死を悦ぶ人間なんて居なかったわ」
「褒め言葉だとしたらありがとう。だって、夢にまで見た世界にもうすぐ旅立てるのよ。これは理想郷(イーハトーブ)なんて比較にならないわ」
「それが、愛恵がいつも言っているぱらいそ?」
「そう。ぱらいそ。天国に最も近い、素敵な死後の世界よ。アンジュちゃんも死神業を辞めて一緒に来ない?」
「それは類人猿に対して、猿真似を止さないかって提案と同じことよ。私は遠慮しておくわ」
「変な譬えね。ざんねーん。もし手紙が書けたら送るね。でも、黄泉の国の住所が分かんないから、インスタの方がいいかな?」
「連絡なんて不要よ。愛恵と関わるのも明後日までだから」
「つれないのね。折角良いお友達になれるかもしれないって、ちょっとだけ思ったのに」

愛恵は頬を膨らませて拗ねていた。友達になれるかも――と思ったのは彼女の本心だったが、アンジュは敢えて聞き流した。個に深入りしないことも規則だからだ。
「もう、この世界に思い残すことは何もない?」
「思い残すことはないけど、まだ最期の願いを聞いてもらってないよ。それを叶えてくれたら、いつ死んでもいいや」
「……そうね。願いを3つ叶えてあげないと、私の死神としての評価に関わるから」
「結局、どこまで行ってもビジネスライクな関係かあ。でも、あたしの最後の願いは、その一線も越えちゃうよ?」
「興味あるわね。どんな願いなのか、教えて」
「あたしが死ぬ前に……愛を、教えて?」
愛恵は上から順に寝間着を脱いだ。下着は身につけておらず、痩せてマネキンのような華奢な肢体が夕焼けに赤く染まる。
その情景は高名な細工師が刻んだ芸術のようだった。見る人が見れば、儚さと、危うさと、妖艶が織り成す現代アートと讃えるだろう。
逆光を浴びた愛恵が口角を上げて笑っている。彼女こそ――魅惑の天使だ。
「アンジュちゃん、セックスしよ」
一糸纏わぬ姿で抱きつくと、無理矢理ベッドに押し倒した。死神に性別はないが、見た目や言動からして愛恵と同性には違いない。少女が、少女に性行為を所望している。
激しく拒絶をするかと思いきや、アンジュは無言のまま愛恵の背中に手を回す。しかと抱擁をした。ひんやりとした、柔らかい肌の感触が伝わる。
「ああ、受け入れてくれるんだ……正直よく分かんないけど、濡れてきたかも。決して偽らず、この瞬間だけでいいから。終わりまで愛してね?」
「愛恵……」
「アンジュちゃん……」
壁に映る二人のシルエットが、ひとつに重なる。シーツに――薄い鮮血が滲む。
【6月23日 午後11時10分】
「昨日は、愛してくれてありがとう。満足だったよ」
初めての情事を思い出して、愛恵は頬を苺色に染めた。内容は殆ど覚えていないようだったが、彼女なりに『これが愛なんだ』と、理解をした。
「そうそう、後一時間もしないで死ぬから、あたしの不幸自慢でも聞いてってよ」
「最後の晩餐ならぬ、最後の愚痴ね。恩情で聞いてあげる」
「えへへ、棘のある言い方だね。あたしは自分の病気について、人生について実はそこまで悲観していないの。こんなあたしの存在なんて、宇宙規模で見ればどうでもいいことでしょ」
「では、何が気に入らなくて、命を粗雑に扱えるの? 担任のことも、カナリアのことも。そして……愛恵が両親を殺したいほど憎んでいることも、私は知っている」
「さっすが、何でもお見通しだね……本当は、3つ目の願いはパパとママを殺してもらおうと思っていたんだけど、辞めちゃった。もう殺すのも飽きた」
飽きたと、愛恵はただ一言そう述べた。この子は、愛を知った振りをしているだけで、中身は何も変わっていないとアンジュはがっかりした。
「貴女の本性が見えてきたわ。何が、そこまで変えたの?」
「うーんとね、退屈かな? 退屈が私を怪物に育てた。怪物と言っても、見かけの話じゃないよ? これでも学年では一位二位の美少女って裏サイトで評判だったから」
愛恵は自分のことを怪物だと紹介した。足を組み、アンジュは黙って話を聞いている。
「いつも、いつも怪物はあたしの頭の片隅に居て、ずっとあたしのことを見ていた。診察の時も、トイレの時も、自慰に耽る時も、ずっとあたしを見ていた」
「その怪物が、愛恵自身だっていうの?」
「ううん、最初は別々の存在だったよ。でも、いつかその境界も曖昧になっていた。気付けば自分が怪物になっていて、あたしの自慰をいやらしく隙間から覗いて、せせら笑っていた」
「そう……」
愛恵の独白は尚も続く――。
「退屈という極上のスイーツを餌に、怪物は急成長していった。でも、怪物が与えたのはきっかけにすぎないと思う」
「同調(シンクロ)してしまったのね」
「うん! あたしの病気はいつしか、心まで蝕んでいた。感情の一部が欠落して、他人に関心を持てなくなってしまったのは、一番の不幸と言えるかもしれない」
「それで……たったそれだけのことで、人を殺してもいい理由になるとは思えない」
嫌悪感を露わにして睨むアンジュに対して、愛恵の表情はとても穏やかだった。諭すように、静かに答える。
「なるよ。少なくとも、あたしの中では。あたしの世界では、咎とは言わない」
「分かったわ。貴女のこと、全て分かった……」
「聞いてくれてありがとう。これで何も思い残すことなくジサツ出来るわ。くすねた劇薬を飲んで、血反吐を撒き散らして、線香花火のように最期は消え入るの」
【6月23日 午後11時58分】
アンジュが呪文を唱え終えて、愛恵は目を開ける。安心して旅立てるよう、言霊が込められているのだろうか。今まで以上に気分が優れているようだ。
病室の窓を全開にする。梅雨の始まりを感じさせる湿っぽい空気が漂っていた。愛恵はそれが自分にとって相応しい終焉だと思っていた。
「心地好い空気……生温くて、肌がべたついて、最高の不快感。最高のステージ」
「安心なさい、もうこれでお別れよ」
「改めて、見付けてくれてありがとう、あたしの天使様。ほら、一足先にシェリーは楽園へと旅立ったわ」
愛恵の手の中にすっぽりと収まったカナリアは、ぐったりと微動だにせず、口から泡を吹き出して息絶えていた。ガス中毒による死だった。
「これで、本当にいいのね。全て貴女が望んだことで、間違いないわね」
「間違いなんてないよ。3つとも全部叶えてくれて、ありがとう」
誠心誠意を込めて愛恵は頭を下げた。これでぱらいそに行ける――そう思って顔を上げた瞬間、凍てつくようなアンジュの視線に背筋がゾクとした。
「アンジュ……ちゃん?」
「まだよ、愛恵……貴女の最期の願いは、これから――」
アンジュの目が赤く輝き、見えざる手で愛恵の肉体を抉り心臓を鷲掴みにする。心と体は分断され、意識を失うとその場に力なく倒れ込んだ。
【????】
目を覚ました愛恵は、真っ暗な世界に居た。冷たい土の感触と、吹き荒ぶ風の音。ここが、彼女が夢にまで見た、ぱらいそなのだろうか――。
「あ、れ……? あたし、どうしちゃったのかな……」
まだ意識がぼんやりとしている。彼女は自分が瞼を閉じたままだったことに気付いた。だから世界が真っ暗闇なのだと、遅れて理解をした。
「そっか、アンジュちゃんがきちんと連れてきてくれたんだよ、ね……? ここが、あたしの待ち望んだ世界――ぱらい、そ……」
愛恵は硬直した。目の前には砂礫と荒野、空に浮かぶ開いたままの扉、生命の存在を感じない何処までも続く地平線。それは楽園とは程遠い光景だった。
「えっ? え、どういうこと? アンジュちゃん? ここって、ぱらいそじゃない。一体何処なの!」
半ばパニックになりながら、出せる限りの声量で張り叫んだ。愛恵の想像するぱらいそとは対局に位置するような、さながらここは死の世界に感じた。絶望と恐怖がのしかかる。
(目が覚めたかしら? これで、貴女の願いは約束通り3つ叶えたわ――)
鈍色の空に浮かぶ扉の奥から声が響いた。それはアンジュの声だった。
「そんな、冗談は止して! こんな願いしてないよね? ここはあたしの知っているぱらいそじゃない!」
愛恵の悲痛な叫びは空に吸い込まれて萎んだ。暫くして、氷のように冷めた返事が届く。
(貴女は最初に言ったじゃない。『自分以外の世界中の人間全てが滅べばいい』って。心の中ではそう願っていると)
「そっ、それは確かに言ったかもだけど……先にあたしは3つ願いを叶えてもらったよ!」
(1つ目の願いはカナリアを生き返らせること、2つ目の願いは愛を教えること、そして、これが3つ目の願いで間違いないわ)
「順番が違う! 最初は担任を殺してって……もしかして、心不全で死んだのって……本当にアンジュちゃんの仕業じゃなくて……ただの病死?」
(自然死だったから、その教師の魂は天使が運んでいったわ。私は傍観者だった)
「そ、そんな……そんな……」
愛恵は虚脱して、その場に膝をついた。不本意な部分もあったが、全て自分の口から出た願いに違いなかった。
(初めから『違う形で願いが叶う』と、『私は何もしていない』と説明をしたわ。それを勝手に勘違いしていたのは貴女の過失でしょう)
「ううっ、ごめんね。帰して……元の世界に、帰して下さい……お願いします、天使様……ひぐっ」
涙と鼻汁を垂らして、顔をくしゃくしゃにしながら愛恵は頭を地面に擦りつけて懇願した。上空では無情にも、扉は徐々に閉まりつつある。
(それは4つ目の願いになるから無理ね。全ての人間が滅んだこの平行世界で、貴女はそこで神として永遠に生き続けなさい。もう、死ぬことすら許されない)
「ああ……元の世界に居るあたしは……どうなったの」
(死んだも同然だけど、行く末を貴女が案ずる必要はないわ。さよなら)
扉が完全に閉じてしまうと、音もなく蜃気楼のようにフッと消えた。愛恵は狂ったように何かを叫び続けていた。
【6月11日 午後2時20分】
「どうして、こんなことに……うう」
女性が両手で顔を覆い、しくしくと啜り泣いている。震える肩を静かに抱き寄せて、隣に並ぶ男性が慰めるように優しく語りかける。
「僕達が一生を賭けて、愛恵に償おう。たとえ意識が、一生戻らないままだとしても」
生命維持装置に繋がれた愛恵の目は虚ろだった。うっすら開いているが、その瞳は混濁して何も映っていない。
ピコン、ピコン、と電子機器の無機質な音が、僅かながら彼女の脳波が動いていることを報せていた。
夜勤に入っていた看護士の話によると、10日の深夜帯にドサッと大きな音がしたらしい。急いで駆け付けると、愛恵が部屋の窓から落ちて地面で倒れていたとのことだった。
足を滑らせたことによる事故だと説明を受けたが、二人は納得していなかった。何故なら、彼女の手首には強く誰かに引っ張られたような痕が残っていたからだ。
「私が……気付いてあげられなかったから。大切にしていたカナリアを亡くして、それから様子がおかしくなったのよ」
女性は唯々後悔して、噎び泣くしかなかった。鳥籠の中には、夕食で出てきた骨付き鶏の食滓が大事そうに納められていた。
男性は愛恵の傍に置かれた一冊の本を手に取ると、何となく表紙を開いて読み始める。パラパラと流し読みをして、数ページ目を通したところで本を机に置く。
「愛恵は……今恐らく楽園の夢を見ているんだと思う。この本の世界のように」
暫くして二人は部屋を後にした。開かれたままの本には、少女をぱらいそへと導く天使が描かれていた。その姿はアンジュに似ていて、少女はとても幸せそうだった。
~前編~ 死神
前ページに戻る